
どうも♪たむ(@tam_tamco25)です^^
この記事では、日本における貧血の姿を本当に詳しく・・・まとめてくださっている
「貧血大国・日本 放置されてきた国民病の原因と対策」という本についてご紹介させていただきます!
本のタイトルを再度読み返しても、本当にダイレクトに伝わってくる言葉だなぁ。と私自身実感しています。
ここからは「後編」の記事となります。
「前編」はこちら▼
※少しずつ、私が個人的にポイントをピックアップしています。省略も多いので、ニュアンスがズレてしまうこともあるかもしれません。ご了承ください。
内容ピックアップ・2
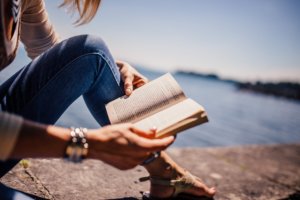
14個ある項目の中で、6〜ご紹介していきます!
1:「何となく体調が悪い」理由
2:貧血のメカニズム
3:体内に不可欠な元素「鉄」
4:美容と貧血
5:妊婦と貧血
6:成人女性と貧血
7:子どもの成長と貧血
8:中高生と貧血
9:アスリートと貧血
10:高齢者と貧血
11:血液検査の読み方
12:何を食べ、どう気をつけるか?
13:ベジタリアンと貧血
14:世界の貧血
それでは行きましょう!
お好みの章がある時は、目次から飛んでくださいね ^^
6:現代女性の病

6つ目は、
成人女性と貧血
についてです。

「今までより生理の量が多くなっている」「生理痛が最近ひどくなった」と感じている方はいませんか?
ここでは、「子宮筋腫」をはじめ、女性特有の疾患 について触れています。
▶︎主な症状は「過多月経」「月経困難症」「不妊」の三つ
▶︎子宮筋腫により月経量が増えると、より多くの鉄を失う
▶︎子宮筋腫ができると貧血になる
▶︎多くの女性は子宮筋腫があっても、なかなか周囲には相談しない
▶︎自覚症状が出てから周囲に相談するまでには、平均3.5年経過している!
月経量が多く、貧血が悪化していくときには、何らかの婦人科疾患が絡んでいる事がよくあるのです。
私自身も、隠れ貧血と月経困難症が一緒に襲ってきました。
本当に辛く、治療をして本当に楽で元気になったので、もし気になる事がある女子のみなさんは本当に1度医療機関に相談してみてください!
7:母から子どもへ

7つ目は、
子どもの成長と貧血
についてです。

子どもが貧血である姿を見たことはありますか?
ここは他の章よりも深く書かれている章でした。それだけの伝えるべき内容があることが文章量からも伝わってくるようでした。
私がその中から ピックアップしたのは2つ です。
①妊娠時の貧血が子どもへ与える影響
母体が重度の貧血の場合、赤ちゃんは成長すると貧血になるリスクが高い
▶︎赤ちゃんがお腹の中にいるときは、母親から鉄をもらう。
▶︎貯蔵鉄(フェリチン)として約4ヶ月分の鉄を持って生まれてくる
▶︎母体が貧血だと、赤ちゃんは生後半年から一年ほどの間に鉄欠乏性貧血を発症してしまう
加えて、
妊娠中期に貧血の場合、早産や低出生体重児の危険性が高まる
という警告も一緒にされていました。
私にとっての学びは、赤ちゃんは貯蔵鉄(フェリチン)として鉄分をもらうという点です。
生まれてきた時は、誰もが鉄分をフェリチンとしても持って生まれてくるんですね。

みなさんのフェリチンはどのくらいですか?
②子どもの貧血と脳の発達
3歳未満の子どもにおける鉄欠乏性貧血と、「貧血にはなっていなくても鉄欠乏状態であること」が神経発達障害に影響を与えることがわかってきている。
▶︎神経発達障害というのは、IQや認知機能、言語能力など、脳への影響のことです。
▶︎バッファロー大学のベイカー医師は、鉄欠乏の危険因子「親の社会経済的地位が低い場合」「低出生体重児の場合」「鉄を補充しないまま母乳栄養で育てている場合」などを挙げています。(さらに衝撃!!)
▶︎日本は貧血対策が全般的に不足していますが、乳幼児期の鉄欠乏生貧血については議論すらされていない
これが1番私の心に刺さった内容でした。
貧血対策をしておくことは、自分のためではなく、将来の子どものために親として事前にしなければならないことでもあると改めて思いました。
8:学生生活を楽しむために

8つ目は、
中高生と貧血
についてです。

学生生活では、何が楽しかったですか?
中高生の貧血は特に放置してはいけません。
▶︎なぜなら勉強にスポーツに励む時間が多くなるから。
▶︎この時貧血では活動に支障をきたすから。
▶︎鉄の欠乏は、貧血を生じないレベルであっても、持久力、勉強や運動の持続力、さらに記憶力を衰退させる ことが報告されています。

このことはどれくらい認知されているでしょうか?
私自身、最初に鉄欠乏性貧血になったのは中学生の時です。
集中力がない人間だと思いこみ、受験勉強に打ち込んできたのですが、実際は真逆の人間であると、社会人になってから気づきました。
ぜひ、みなさんには中高生のうちに気づいて対処してほしいです!
9:筋肉量が多い=貧血リスク「高」

9つ目は、
アスリートと貧血
についてです。

スポーツしている人に貧血が多い、という事実をご存知でしょうか??
「スポーツ貧血」の原因
▶︎①「鉄の摂取不足」:筋肉量が多い
ミオグロビンが多い ➡️ ビンには鉄分が含まれている ➡️ より鉄分が必要!
▶︎②「発汗による鉄の喪失」
スポーツなどでの急激な発汗では、汗とともに多くの鉄分が失われてしまう。
▶︎③「スポーツによる衝撃」
足の裏や体に衝撃がかかった時、血液中の赤血球が破壊される。
(通常は身体の中で再吸収されるが、ひどい時は血尿が出ることもある。)
とても基本的なところだけピックアップしたのですが、これだけでもスポーツと貧血の関係性を実感できますよね。
筋肉量が多いことは健康的ではありますが、より鉄分が必要な身体になります。
私自身も、そういえば筋肉量が多い女子として生きているな…と再発見の場になりました!
10:高齢と病と貧血

10つ目は、
高齢者と貧血
についてです。
この章は、他の章と比べても別格の場所にあります。
それだけ、
高齢者の貧血の多くは病気とダイレクト関係していることが多いです!
ヘモグロビン濃度は加齢とともに低下する
▶︎理由①:骨髄の造血幹細胞の老化(血を新しく作る力が弱まる)
▶︎理由②:腎臓のエリスロポエチン分泌能力の低下(赤血球の源を作る力が弱まる)
▶︎理由③:男性ホルモン分泌能力の低下(!)
▶︎男性ホルモンは、筋肉量を増やしたりする以外に、赤血球の産生を促す働きがある!
男性ホルモンって、すごいですよね!
それも含めて、女性ではなく男性に生まれたかったな…と思う私でした。。
他にも、服薬の副作用での貧血や、消化器官が弱まったり、切除することによる貧血、貧血の症状は高齢者の方がそもそも日々感じやすい状態であるため気付きにくい点など、貧血に気づいた時は本当に悪い状態となっていることが多い。というところに、大きな注意点があるとのことです!
(他にも書ききれないくらいの注意点と想いが詰まっていました。)
11:血液検査をすることは、どれだけ大切なことか?
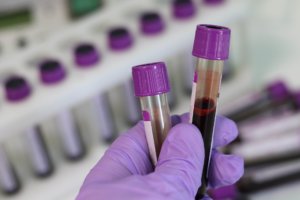
11つ目は、
血液検査の読み方
についてです。
ここでは、貧血に関する数々の検査項目について、医師の目線から解説されている章です。
血液検査の項目を理解できますか?(フェリチンをピックアップしました。)
▶︎実際に体内で鉄が不足しているか否か調べるもの=フェリチン濃度
▶︎生体内で、鉄を貯蔵する役割を果たしています。
▶︎鉄剤を投与すると、貧血は数週間で回復するのですが、この状態で鉄剤を中止すると、すぐ元の状態に戻ってしまいます。
▶︎臨床医は、血液中のフェリチン値が正常化するまで、鉄剤を継続して処方します。
貧血について知ることは、今の健康状態を知り、食生活を見直すきっかけとなるだけでなく、背後に潜んでいるかもしれない、より大きな病気の早期発見にもつながることであり、その手がかりとして、血液検査は重大な意味を持つ。
『とても深い言葉だな…』と私自身刺さった一文でした。
12:基本だけれど、すごく影響が大きい「食事」

12つ目は、
何を食べ、どう気をつけるか?
についてです。

ヘム鉄と非ヘム鉄、私たちが多く摂取しているのはどちらでしょうか?
別記事にしたく思っているほど、内容が濃く・とても実践的です!
口から入れる食事などによって、体内の鉄分は絶妙にコントロールされていることを目の当たりにする。
最も印象に残る章でした。
日本人が食事で摂取している鉄の多くは「非ヘム鉄」
▶︎ヘム鉄 は、そのまま消化吸収され、体内で利用される。非ヘム鉄 は、消化吸収されにくい鉄。
▶︎ヘム鉄 は、魚介類(イワシ、干しエビ、あゆ、シジミなど)肉類(レバー、馬肉、牛ヒレ)など。
▶︎非ヘム鉄 は、豆類(きな粉、油揚げ、ゆば、納豆)、パセリ、小松菜など。
▶︎注目の食材は「海苔」
豆類は私もおすすめの食品の1つですが、海苔はとても意外中の意外でした!
これ以外にも、調理法や食べ方、サプリメントや鉄剤をより飲みやすくする方法に至まで、本当に詳し
く書かれています。
そして、最後の言葉はとても響く内容でした。
鉄欠乏貧血を鉄剤によって改善するには、長い期間が必要です。
貧血が私たちの体にもたらす影響は想像以上に大きいことをご理解いただいた上で、ひとりでも多くの人に貧血の治療を受けていただきたい!
13:野菜をたくさん食べる弊害

13つ目は、
ベジタリアンと貧血
についてです。
ベジタリアンについて、とても丁寧に説明を入れた上で、日本人が貧血になりやすい理由まで導き出しています。
(私のピックアップが甘いかもしれません。ご了承ください。)
▶︎ベジタリアンは、肥満、高血圧、糖尿病、心臓疾患、がんのリスクが低いことが示唆されている。
▶︎肉を摂らないことで、たんぱく質が不足すると、鉄・カルシウム ・亜鉛、ビタミンB12・ビタミンDが不足がちになり、健康に悪影響を与える。
▶︎日本人は、意識しないまま、ベジタリアンと似た食生活を送ってきた
▶︎遺伝的に肉類を消化することが得意でない日本人にとって、肉類を多く摂取しないのは好ましいこととも言えるのですが、それが極端になると、鉄欠乏性貧血を生じる。
日本人の食文化には、もともとそうなりやすい傾向がある。
文化的なもの、習慣的なものの中に、プラスして、生理の回数が多いことが追い風になってしまっているのかな…と、私自身『より頑張らなくては!』と感じるきっかけとなりました。
14:世界から見た「貧血大国・日本」

14つ目は、
世界の貧血
についてです。
日本の貧血の現状を、地球地図を巡るように広い視点で眺めさせてくれます。
たくさんの論文を扱う章なので、説得力もとても強かったように感じました。
全世界の人口のうち、約20億人が貧血と見なされています。(世界人口の約28%)
▶︎貧血の原因の95%は、鉄分の乏しい食生活=「貧血は、世界でもっともありふれた栄養不足の一つ」
▶︎先進国の貧血の原因は、不適切なダイエット / 偏った食事 / 鉄分の吸収を疎外する薬剤や食品の利用
そして、、
日本の貧血対策の現状は、「ほとんど無策」です。
特に、将来の自分のためだけでなく、生まれてくる赤ちゃんのためにも、妊婦や妊娠を控えている女性、そして妊娠を考えている女性への早期の貧血対策は必須だと思います。
女性がもっと働きやすい社会を作るためにも、有用でしょう。
日本が「貧血対策の先進国」となることを、医師として心から願っています。
抜粋を挟んでおりますが、最後のこの言葉に、筆者の想いが強く込められていると、私は強く思いました。
私自身も筆者の願いが叶う日がくるように、微力ながら力を込めていけたらと思っています!
まとめ
ここまで、「貧血大国・日本 放置されてきた国民病の原因と対策」についてご紹介を書いてきました。
6:月経量が多く、貧血が悪化していくときには、何らかの婦人科疾患が絡んでいる事がよくある
7:母体が重度の貧血の場合、赤ちゃんは成長すると貧血になるリスクが高い
8:貧血を生じないレベルであっても、持久力、勉強や運動の持続力、さらに記憶力を衰退させる
9:筋肉量が多いことは健康的ではありますが、より鉄分が必要な身体になるということ
10:男性ホルモンは、筋肉量を増やしたりする以外に、赤血球の産生を促す働きがある!
11:貧血について知ることは、今の健康状態を知り、食生活を見直すきっかけとなるだけでなく、背後に潜んでいるかもしれない、より大きな病気の早期発見にもつながることであり、その手がかりとして、血液検査は重大な意味を持つ
12:注目の食材は「海苔」/鉄欠乏貧血を鉄剤によって改善するには、長い期間が必要!
13:遺伝的に肉類を消化することが得意でない日本人にとって、肉類を多く摂取しないのは好ましいこととも言えるのですが、それが極端になると、鉄欠乏性貧血を生じる。
14:日本の貧血対策の現状は、「ほとんど無策」
少し長いですが、まとめさせていただくとこのようになります。
ここまで、貧血について記事を書くことを楽しみとする私でも、たくさんの学びと発見がいっぱいでした。
もちろん、基本的な情報も書かれつつ、深いところまで着き詰めてあることが、優しい本の良いところであると感じます。
それぞれのペースに合わせて読んでいただける1冊です^^
記事の中では、とても短くピックアップさせていただいているため、筆者の思いは十分に伝えることが難しい内容になっていると反省しています。
そのくらい本に詰まっているものは多いので、もし興味を持ったら、ぜひポチってください♪
これからに繋がってくるきっかけになるかもしれません!

\LINE公式アカウントお友達登録はこちら/
🎁「貧血の対策マニュアル10選」無料プレゼント中です🎁

もし、貧血の知識ではなく、
『貧血の悩みや不安を相談したいな。』
という場合は、こちらがおすすめです!
\貧血相談窓口はこちらから/

● 貧血特化オンラインサロン「Anemi(アネミー)-たむによる貧血女子が元気になる秘密基地-」


最後まで読んでくださりありがとうございました!




コメント